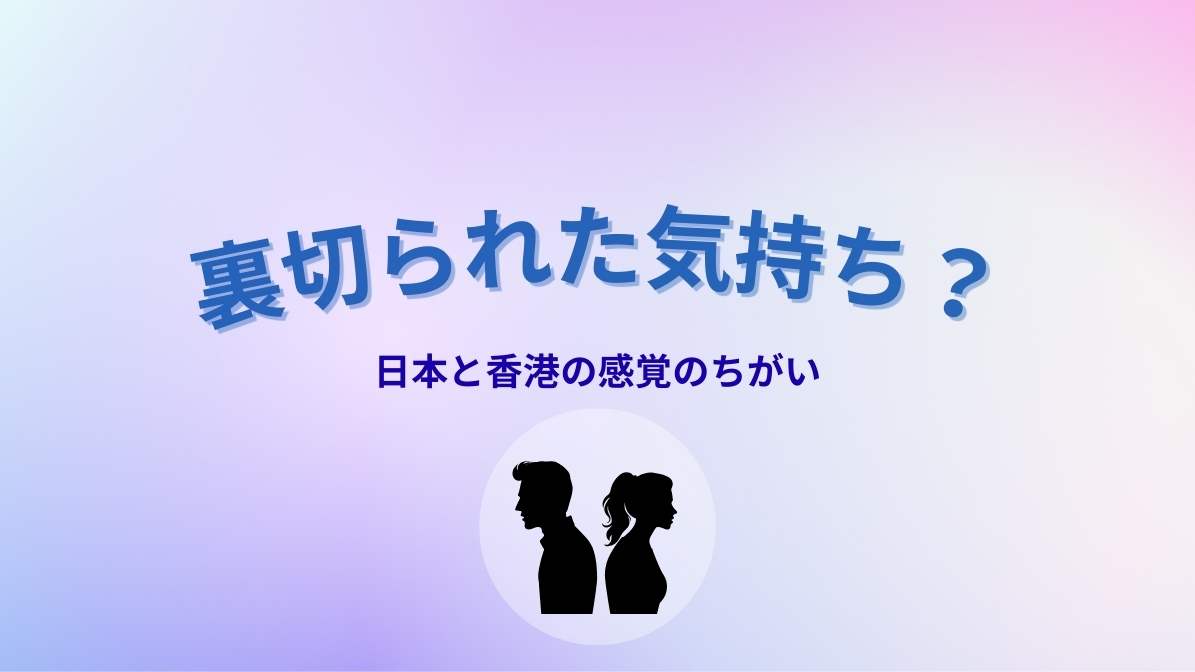ニュースから始まった会話
先日、神戸で起きた殺人事件のニュースについて日本語学習者さんと話していました。
ニュースの中で容疑者の上司のコメントが紹介されていました。
「裏切られた気持ちでいっぱいです」
この言葉について、香港出身の学習者さんがこう言ったのです。
「先生、中国語ではこういうとき『裏切られた』は使わないですよ。直接自分に何かされたわけではないから…」
その一言に、私はハッとしました。
同じ「裏切る」という言葉でも、日本語と広東語(中国語)の使い方には大きな違いがあるのです。
日本語の「裏切る」は広い意味で使う
日本語では「裏切る/裏切られた」という表現を、とても広く使います。たとえば、次のようなときに「裏切られた」を使うのではないでしょうか。
- 恋愛関係で相手が浮気をした。
- 友人に金を貸したら返さずにいなくなってしまった。
- 秘密にしてほしいと頼んだことをばらされた。
また、必ずしも「直接だまされた」「約束を破られた」といった事実がなくても、信頼や期待を壊されたときにも自然と「裏切られた」という表現を使っています。
- 部下が事件を起こして「裏切られた気持ち」になる。
- 応援していた選手が不祥事を起こして「裏切られた」とSNSに書き込む。
- 突然結婚したアイドルのSNSが「ファンを裏切った」と炎上する。
つまり、日本語では 「自分が期待していたイメージと違う行動をされたとき」 にも「裏切り」という言葉を使うのです。
ですから、ニュースの上司の発言を聞いても日本人は違和感を覚えることはありません。
広東語・中国語では「背叛」は限定的
一方で、香港人の学習者さんによると、広東語や中国語の「背叛」「出賣」は直接的な意味合いでしか使わないのだそうです。
秘密をバラされたというような「自分に直接的な不利益がある場合」 に使うのが一般的で、ニュースの上司の発言のような状況では不自然になるそうです。
代わりに使うのは:
- 失望了(とても失望した)
- 很震惊(大きなショックを受けた)
- 心寒(心が冷えた、がっかりした)
- 没想到他会这样(まさかこんなことをするとは思わなかった)
香港人の学習者さんいわく、この方が自然に気持ちを表せるのだそうです。
「組織意識」という視点
さらに印象的だったのは、その学習者さんがこう言ったことです。
「日本人は組織を意識するから、部下の事件に対しても『自分が裏切られた』と感じるのでは?」
これはとても鋭い視点だと思いました。
- 日本人:会社や組織への帰属意識が強く、部下の行為も「自分や組織への裏切り」と感じやすい。
- 香港人/中国人:より個人の関係を重視するので、「自分が直接被害を受けたかどうか」で言葉を選ぶ。
つまり、「裏切り」の感覚の広さの違いは、言葉だけでなく文化的な価値観の違いも映し出しているのです。
言葉の背景にある文化を学ぶ
このやりとりを通して感じたのは、言葉の使い分けを学ぶことは、その背景にある文化や考え方を学ぶことでもあるということです。
- 日本語:「気持ちの揺れ」を中心に表現
- 中国語・広東語:「事実や直接的な関係」を中心に表現
同じ「裏切り」という言葉でも、感覚の広さや使い方が違う。
その違いを知ることで、日本語をより自然に理解できるし、日本社会の価値観にも気づくことができます。
おわりに
ニュースの一言から生まれた香港人学習者さんとの会話は、言葉の勉強を超えて「日本人と香港人のものの見方の違い」を教えてくれました。
「裏切られた気持ち」という表現には、日本人の組織意識や信頼の文化が映し出されています。
一方、香港人の感覚では「失望」「心寒」といった言葉がより自然に響きます。
言葉の選び方には、その社会の価値観や人間関係のあり方が反映される。
だからこそ、日本語を学ぶときは、単語の意味だけでなく「どういう場面で使うのか」「どんな文化背景があるのか」にも目を向けていきたいですね。